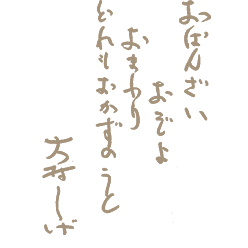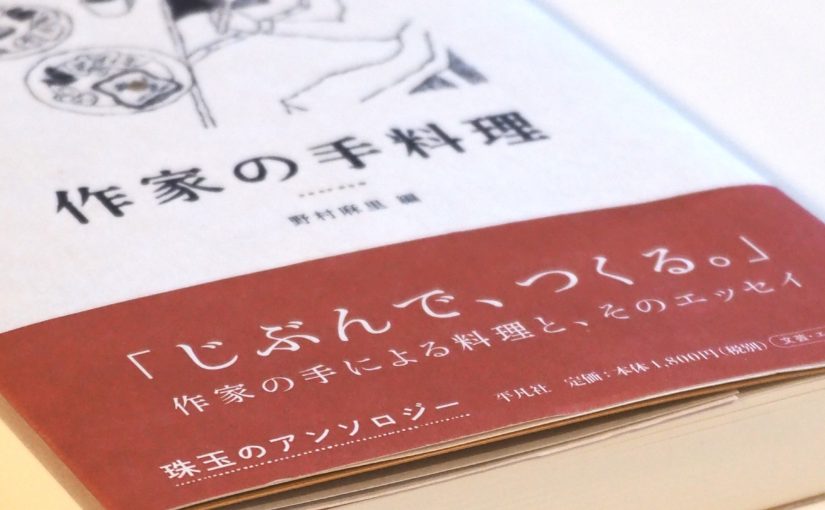2021年2月末、平凡社から『作家の手料理』が発売になりました。この本は30名の作家が書いた料理にまつわる随筆集で、大村しげさんの作品も一遍、選ばれています。
編集を担当された、野村麻里さんに『作家の手料理』の企画意図や、大村さんへの思いを聞きました。
プロフィール/野村麻里さん
ライター・編集者。1965年東京生まれ。著書に『ひょうたんブック』『香港風味』、編著に『作家の別腹』『南方熊楠 人魚の話』、翻訳にリトルサンダー『わかめとなみとむげんのものがたり』などがある。
―最初に『作家の手料理』の企画背景や、意図についてお聞かせください。
長い間、仕事で作家と食に関する取材をしていたので、食随筆は個人的にも好きでした。食随筆には2種類あって、本人が作る場合と(他者が作った料理を)食べるだけのものがあります。私自身が料理好きということもあって、作る人の随筆のほうが好きなものが多いと思っていました。
2007年に『作家の別腹 文豪の愛した東京・あの味 (知恵の森文庫)』(光文社)を出版したあたりから、“作る人”の食随筆だけをまとめるアイデアは持っていて、機会があれば、と資料を集めていました。

『作家の手料理』 平凡社 定価1980円(本体1800円+税)
https://www.heibonsha.co.jp/book/b553130.html
―長く、企画を温めていらしたわけですね。
そこから、ずいぶん時間が経って、今回のコロナ騒動が起こりました。平凡社の編集の方から、外出できない中、なにか本のアイデアはない? と問われ、「料理のアンソロジー(選集)はどうですか?」と答えたのが、今回の出版となったのです。家でできる、家にいることを意識して助けになる読み物をと考えて生まれた企画でした。コロナ禍で自宅での調理が注目されたこともありましたから。
-今回、30名の作家のなかに、大村さんの作品を選ばれたのはどうしてですか?
私が初めて大村さんの随筆を知ったのは1990年代、荻 昌弘さんが編集した『世界の名筆集59 菜』(作品社)に収録された「煮炊き」だったと思います。本の一番初めに登場するのが大村さん。すごくいい文章だと思いました。京都の言葉を使って書く方はほかにもいるけれど、京ことばを使いながらの文章のまとめ方がとても上手で。だから、手料理のアンソロジーを作るなら、大村さんの作品を絶対に入れたいと思っていたんです。
-そして、選ばれた随筆が「ほっしんとはなくそ」だった理由をお聞かせください。
大村さんの著作の中で私が特に好きなのは『冬の台所』(冬樹社)と『しまつとぜいたくの間』(佼成出版社)です。いま、京都で料理について書く方は、「しまつ」について取り上げることが多いですよね。でも、「しまつ」は生活や習慣から自然に理解するものですから、核心をつかめる文章はなかなかありません。大村さんはたびたび、「しまつ」について書かれていて、これを読んで私も、「しまつ」とは、なにかを理解できました。
注釈:
「ほっしんとはなくそ」、「しまつ」について
「ほっしん」とは、お釜の底についたおこげを崩して、乾燥させ、パラパラにしたものです。大村さんのおばあさんは、これを無駄にせず、缶に入れて保存食とし、ときにはほっしんを使ってお菓子を作っていました。「ほっしんとはなくそ」には、おばあさんがほっしんを大事にしていた理由が、関東大震災に由来する防災の備えであったと書かれています。
京都では、ものを無駄にしないことを「しまつ(する)」と表現します。大村さんの時代には、この考え方がまだ根強く、彼女はそれを徹底していました。ものに与えられた命を粗末にせず、最後の最後まで役割を与えて使い切る。無駄を嫌い、命を全うさせることに美徳を感じる考え方です。そして、彼女の「しまつ」は、生活道具や衣類、食材など、暮らし全般に及んでいました。
「しまつ」について、彼女は文化だと考えていたでしょうし、分からない人に「しまつとはなにか?」を伝える難しさ、「しまつ」のよさも理解されていたんだと思います。ケチとしまつは違うのですが、私はケチですから「しまつ」にも興味があったんですよね(笑)。
今回の「ほっしんとはなくそ」は、「米粒が……」って話が、関東大震災や防災につながる、実はスケールの大きな作品です。街の歴史と米粒が文章の中でうまくつながってくる。
-その意外性、「しまつ」の精神に魅力があるというわけですね。
そうです。いま「しまつ」は京都を象徴する言葉のひとつとなっていて、料理研究家のなかにも「しまつ」という言葉を使いたい方が増えています。でも、この作品はそうじゃない。要素のつなげ方が面白い。やっぱり単なる生活雑記と大村さんの随筆って違うものなんですよね。
―『作家の手料理』には、大村さんと一緒に『おばんざい』(※)を書かれた、秋山十三子さんの作品も収録されていますね。
※1960年代、大村しげさん、秋山十三子さん、平山千鶴さんの3名による、朝日新聞京都版上での連載。「おばんざい」という言葉を普及させるきっかけとなり、のちに書籍化された。昨年、河出書房新社より『おばんざい 京の台所歳時記(春と夏、秋と冬の2冊構成)』として文庫化。
平凡社で『作家の酒』をつくった時、秋山さんのご家族に取材したんですね。その際、ご子息の奥様が、当時の料理を再現してくださいました。秋山さんは淡々と(暮らしや料理の)ディテールを細かく書いてくださっていて、私は秋山さんの文章も大好きです。平山さん(※)もそう。『おばんざい』のお三方のように、地域の生活を正確に描写して書かれたものは、以前は広く読まれる機会がなかなかなかったように思います。
※平山千鶴さん。『おばんざい』を連載した3名の随筆家のおひとり。
―今回、秋山さんの作品は「山科なす」。選ばれた理由が知りたいです。
題材の山科なすといえば京野菜のひとつ。最近では、地元の魅力を再認識する機運が高まっていますから、ちょうどいいなと。文面からすると、書かれた時代は、ちょうど山科なすがなくなってしまうかも、という時代ですよね。秋山さんのように、地元の食材を大事にしている方がいたからこそ、地元の特産物が残ったんだと思います。

―野村さんにとって大村さんとはどんな存在ですか?
まず、私は彼女のファンなんです。大村さんの料理についての文章を読んで実際、いろんな料理を作りました。そしていまは、フェミニズムの流れもあり、女性が表現する時に、壁となる問題を解決していこうという気運が起こりはじめています。大村さんは物書きとして一生を通した方ですよね。文章や資料を読むと、生き方に筋が通っていると感じます。
―「筋が通っている」と思われた具体的な点はありますか?
自ら「わたしはすごくわがままだから、結婚に向いていない」というようなことを何度か書いています。彼女は、なぜ結婚しなかったか、なぜ物書きで一生を終えたかを数行で書けてしまうんです。潔いな、と私などは思います。
―大村さんにフェミニズムをお感じになることは?
一人で暮らす。結婚もしないし、子供もいない。書くことを生業として生きる人は作品が自分そのものを表現しています。彼女はフェミニズムという言葉も使わないけれど、彼女が自分の生活を描写した文章から、女性が表現するとは、どういうことなのかが伝わります。夜中に原稿を書く人だったそうで、そういう、自分で選んだ生活を楽しんでいるところも私は好きです。
-生き方が、一般的な家庭の主婦とは違いますよね。
そうそう、そういう人がおばんざいの代表者になった点に興味を惹かれます。本来、暮らしや家庭料理にまつわる話題を書く人となれば、結婚をして家庭のあった秋山さんのほうがおばんざいの代表的なイメージに近いでしょう。秋山さんのほうが王道なんですよ。
大村さんの生き方も非常におもしろくて。晩年、バリ島へ移住したのも潔い。あれだけ「京都」のことを書いていたのに、移住後も全然つらそうな感じがないんですよね。
-大村さんの作品をどんな方に読んでほしいですか?
もちろん、男性、女性を問わず、若い世代に大村さんの文章をもっと読んでほしいですね。書き言葉の中に京ことばを取り入れて京都の暮らしを描き、家庭を持たずに家庭料理であるおばんざいを世に知らしめた。こういう不思議なバランスで素晴らしい文章を書いた人がいらしたことを、もっとたくさんの方に知ってほしいです。
-大村さんの生き方や随筆が、多くの人の支えになるといいですね。『作家の手料理』がそのきっかけになることを期待しています。どうも、ありがとうございました。